
иӢұиӘһгҒ§"-gh"гӮ„"kn-"гҒ®"k"гҒӘгҒ©иӘӯгҒҫгҒӘгҒ„еӯ—гӮ’гҖҢй»ҷеӯ—гҖҚгҒЁгҒ„гҒ„гҖҒ
жҳ”гҒҜзҷәйҹігҒ—гҒҹгҒҢгҖҒжҷӮд»ЈгҒ®жөҒгӮҢгҒ§зҷәйҹігҒ•гӮҢгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҖӮ
пјҲ"kn-"гҒ®"k","wr-"гҒ®"w"гҒӘгҒ©пјүгҖҒ
жҷӮд»ЈгҒ®жөҒгӮҢгҒ§зҷәйҹігҒҜеӨүеҢ–гҒ—гҒҹгҒҢз¶ҙгӮҠгҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©еӨүгӮҸгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒҢиҰҒеӣ гҖӮ
гҒёгҒҲ
гҒҫгҒҹиӘһе°ҫгҒ®"e"гҒҜжҳ”гҒҜгҖҢгӮЁгҖҚгҒЁгҒҜгҒЈгҒҚгӮҠзҷәйҹігҒ—гҒҹгҒҢ
д»ҠгҒҜгҖҒ"e"гҒ®еүҚгҒ®жҜҚйҹігҒҢ
дҫӢгҒҲгҒ°"a"гӮ’гҖҢгӮЁгӮӨгҖҚгҒӘгҒ©гҒЁзҷәйҹігҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®зӣ®еҚ°гҒЁгҒ—гҒҰж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
еҚҳиӘһгҒ®дҫӢпјҡtimeпјҲгғҶгӮЈгғјгғЎвҶ’гӮҝгӮӨгғ пјүгҖӮ
гҒҫгҒҹisland гҒ®"s"гӮ„гҖҒreceiptгҖҖгҒ®"p"гҒӘгҒ©гҒҜ
еҸӨгҒ„гғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ®иЁҖиӘһгҒ®з¶ҙгӮҠгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰж•ўгҒҲгҒҰжӣёгҒҚе…ҘгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҖӮ
зҙ зӣҙгҒ«жҲҗгӮӢзЁӢгҒқгғјгҒӘгӮ“гҒ
й»ҷеӯ—пјҲгӮӮгҒҸгҒҳпјүгҒЁгҒҜгҖҒеҚҳиӘһгӮ„ж–ҮгӮ’иЎЁгҒҷз¶ҙгӮҠгҒ®дёӯгҒ§гҖҒ
зҷәйҹігҒ•гӮҢгҒӘгҒ„иЎЁйҹіж–Үеӯ—гӮ„гҖҒиӘӯгҒҝдёҠгҒ’гӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®гҒӘгҒ„еӯ—зҙ гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ
жҰӮиҰҒпјҡеӨҡгҒҸгҒ®иЁҖиӘһгҒ®иЎЁиЁҳзі»гҒ«еӯҳеңЁгҒ—гҖҒгҒЁгҒҸгҒ«иЎЁйҹіж–Үеӯ—гҒ«гӮҲгӮӢиЎЁиЁҳзі»гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒ
зҸҫеңЁгҒ§гҒҜзҷәйҹігҒ•гӮҢгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹеҸӨгҒ„йҹігҒ®з—•и·ЎгҒҢз¶ҙгӮҠдёҠгҒ«йҒәгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒҢеӨҡгҒ„гҖӮ
гҒ»гҒӢгҒ«гҖҒеҖҹз”ЁиӘһгҒ§гӮӮгҒЁгҒ®иЁҖиӘһгҒ®иЎЁиЁҳгҒ«еҖЈгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гӮ„гҖҒеҗҢйҹіз•°зҫ©иӘһгӮ’еҢәеҲҘгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«
гҒӮгҒҲгҒҰжҢҝе…ҘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ
иӢұиӘһгҒ®иӘһжң«гҒ® e гӮ„ gh гҒӘгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгҒқгӮҢиҮӘдҪ“гҒҜзҷәйҹігҒ—гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒ
еүҚеҫҢгҒ®жҜҚйҹіеӯ—гҒӘгҒ©гҒ®зҷәйҹіж–№жі•гӮ’зӨәе”ҶгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘеҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%99%E5%AD%97
гҒҹгӮҒгҒ«гҒӘгӮӢгҒӘгҒҒ
|
|
гҒ“гҒЎгӮүгӮӮеҸӮиҖғгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮWikipediaпјҡеӨ§жҜҚйҹіжҺЁз§»
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%AF%8D%E9%9F%B3%E6%8E%A8%E7%A7%BB
еӨ§жҜҚйҹіжҺЁз§»пјҲгҒ гҒ„гҒјгҒ„гӮ“гҒҷгҒ„гҒ„пјүгҒЁгҒҜгҖҒгӮӨгғігӮ°гғ©гғігғүгҒ®иЁҖиӘһгҒ§гҒӮгӮӢиӢұиӘһгҒ®жӯҙеҸІдёҠгҖҒ
дёӯиӢұиӘһжңҹеҫҢжңҹпјҲ1400е№ҙд»ЈеҲқй ӯпјүгҒ«гҒҜгҒҳгҒҫгӮҠгҖҒ
иҝ‘д»ЈиӢұиӘһжңҹпјҲ1600е№ҙд»ЈеүҚеҚҠпјүгҒ«е…ҘгҒЈгҒҰе®ҢдәҶгҒ—гҒҹгҖҒ
жҜҚйҹідҪ“зі»гҒ®дёҖйҖЈгҒ®жӯҙеҸІдёҠгҒ®еӨүеҢ–пјҲвҶ’иӢұиӘһгҒ®йҹійҹ»еҸІпјүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
жңҖеҲқгҒ«з ”究гӮ’иЎҢгҒЈгҒҹиЁҖиӘһеӯҰиҖ…гӮӘгғғгғҲгғјгғ»гӮӨгӮ§гӮ№гғҡгғ«гӮ»гғігҒ«гӮҲгӮӢ
иӢұиӘһгҒ®иЎ“иӘһGreat Vowel ShiftгҒ®зӣҙиЁігҖӮжҜҚйҹіеӨ§жҺЁз§»гҒЁгӮӮгҒ„гҒҶ
гҒҫгҒҹгҖҒforeignгӮ„signгҒ®"-gn"гҒ®"g"гӮӮиӘӯгҒҫгҒӘгҒ„гҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҜ"gn"гҒЁгҒ„гҒҶз¶ҙгӮҠгҒҢгғ©гғҶгғізі»пјҲгғ•гғ©гғігӮ№иӘһгҒӘгҒ©пјүгҒ§
гҖҢгғӢгғЈгғ»гғӢгғҘгғ»гғӢгғ§гҖҚгҒ®иЁҖгҒ„еҮәгҒ—гҒ®зҷәйҹігӮ’иЎЁиЁҳгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҖӮ
гҒӨгҒҫгӮҠforeignгҒҜгҖҢгғ•гӮ©гғјгӮҢгӮӨгғігғӢгҖҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҷәйҹігҒ гҒЈгҒҹгҒҢгҖҒ
иӢұиӘһгҒ«гҒҜгҖҢгғӢгғЈгғ»гғӢгғҘгғ»гғӢгғ§гҖҚгҒ®зҷәйҹігҒҢдҪҝгӮҸгӮҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§
"g"гӮ’з„ЎиҰ–гҒ—гҒҰгҖҢгғігҖҚгҒЁзҷәйҹігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
й»ҷеӯ—гӮ’гҒҫгҒЁгӮҒгҒҰгҒҝгӮӢгҖӮ
b: t гҒ®еүҚгҒ® b пјқdoubt, debt, subtle
m гҒ®еҫҢгҒ® b пјқbomb, climb,comb, tomb, womb,plumb, plumber
c: muscle, indictгҖҖд»–
d: Wednesday, handkerchief,sandwich пјҲd гӮ’зҷәйҹігҒҷгӮӢе ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮӢпјү
g: foreign, sign, design, paradigm, campaign,
sovereign,gnaw, gnu, gnarl
дәҢйҮҚжҜҚйҹігғ»й•·жҜҚйҹігҒ®еҫҢгҒ®gh: fight, high, night, light, right,dough,
bough, thigh, droughbought, brought, caught, daughter, taught гҒӘгҒ©
h:пјҲеҚҳиӘһгҒ®жңҖеҲқгҒ«гҒӮгӮҠгҖҒжҜҚйҹігҒ®еүҚгҒ® hпјүheir,hour,honest,honor
kn- гҒ® k: knack, knee, knicker, knight,knit, knot, knowlege
n:пјҲm гҒ®еҫҢгҒ® n пјүautumn, hymn, comdemn, solemn
пјҠatutumnal гҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒn гӮ’зҷәйҹігҒҷгӮӢгҖӮ
p:cupbord,psychology, pneumonia,receipt
ps: corps
s: aisle, debris, island, isle
t: often
sгҒ®еҫҢгҒ®пҪ”: castle, Chirstmas, fasten, hustle,
listen, wrestle, whistle
жҜҚйҹігҒ®еүҚгҒ®u: guard, guitar, guess, guest
w: sword
r гҒ®еүҚгҒ® w пјқwrite, wreath, wrinkle, wrap, wrong
дё»гҒӘжҜҚйҹіеӨүеҢ–пјҡ
й•·жҜҚйҹі[a:]гҒҜгҖҒдәҢйҮҚжҜҚйҹівҶ’[e?]гҒёгҒ®еӨүеҢ–гҖӮпјҲnameгҒӘгҒ©гҖӮгҖҢгғҠгғјгғЎгҖҚвҶ’гҖҢгғҚгӮЈгғ гҖҚпјү
й•·жҜҚйҹі[Оө:]гӮ„[e:]гҒҜгҖҒй•·жҜҚйҹі[i:]гҒёгҒ®еӨүеҢ–гҖӮпјҲfeelгҒӘгҒ©гҖӮгҖҢгғ•гӮ§гғјгғ«гҖҚвҶ’гҖҢгғ•гӮЈгғјгғ«гҖҚпјү
й•·жҜҚйҹі[i:]гҒҜгҖҒдәҢйҮҚжҜҚйҹі[a?]гҒёгҒ®еӨүеҢ–гҖӮпјҲtimeгҒӘгҒ©гҖӮгҖҢгғҶгӮЈгғјгғЎгҖҚвҶ’гҖҢгӮҝгӮЈгғ гҖҚпјү
й•·жҜҚйҹі[?:]гҒҜгҖҒдәҢйҮҚжҜҚйҹі[o?]гҒёгҒ®еӨүеҢ–гҖӮпјҲhomeгҒӘгҒ©гҖӮгҖҢгғӣгғјгғЎгҖҚвҶ’гҖҢгғӣгӮҘгғ гҖҚпјү
й•·жҜҚйҹі[o:]гҒҜгҖҒй•·жҜҚйҹі[u:]гҒёгҒ®еӨүеҢ–гҖӮпјҲfoolгҒӘгҒ©гҖӮгҖҢгғ•гӮ©гғјгғ«гҖҚвҶ’гҖҢгғ•гғјгғ«гҖҚпјү
й•·жҜҚйҹі[u:]гҒҜгҖҒдәҢйҮҚжҜҚйҹі[a?]гҒёгҒ®еӨүеҢ–гҖӮпјҲnowгҒӘгҒ©гҖӮгҖҢгғҢгғјгҖҚвҶ’гҖҢгғҠгӮҰгҖҚпјү
гӮҸгҒҡгҒӢ200пҪһ300е№ҙгҒЁгҒ„гҒҶзҹӯжңҹй–“гҒ«
гҒ“гӮҢгҒ»гҒ©гҒ®еӨүеҢ–гҒҢиө·гҒҚгҒҹеҺҹеӣ гҒҜзү№е®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮүгҒҡгҖҒ
зҸҫеңЁгӮӮи¬ҺгҒ®гҒҫгҒҫгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒ
й»’жӯ»з—…пјҲгғҡгӮ№гғҲпјүгҒ«гӮҲгӮҠе°‘ж•°гҒ®зҹҘиӯҳйҡҺзҙҡгҒ®дәәгҖ…гҒҢжӯ»гӮ“гҒ гҒҹгӮҒгҖҒ
еӨ§еӨҡж•°гӮ’еҚ гӮҒгӮӢдёӢеұӨйҡҺзҙҡгҒ®дәәгҖ…гҒ®й–“гҒ§дҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹзҷәйҹігҒҢ
иЎЁгҒ«еҮәгҒҰгҒҚгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶиӘ¬гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ
и©©гӮ„жӯҢгҒ®гғ©гӮӨгғ пјҲйҹ»пјүгҒ®гҒӣгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒ‘гҒ©йҒ•гҒҶгҒ®гҒӢ
гҒ„гӮ„еӨ–еӣҪиӘһиӢҰжүӢгҒ гҒӢгӮүйҒ©еҪ“гҒ«жҖқгҒЈгҒҹгӮ“гҒ гҒ‘гҒ©
иӢұиӘһгҒқгӮ“гҒӘгҒ«еӢүеј·гҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ‘гҒ©гҒ“гҒҶгҒ„гҒҶж•ҷйӨҠгҒҜеҘҪгҒҚ
гҒЎгҒӘгҒҝгҒ«дё–з•ҢдёҖй»ҷеӯ—пјҲзҪ®гҒҚеӯ—пјүгҒҢеӨҡгҒ„иЁҖиӘһгҒҜгғҒгғҷгғғгғҲиӘһгҒ гҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
еҸӨејҸгӮ’гҒ»гҒјиёҸиҘІгҒҷгӮӢгғҒгғҷгғғгғҲж–Үеӯ—гҒ®з¶ҙгӮҠж–№гҒҜгҖҒ
зҸҫеңЁгҒ®зҷәйҹігҒЁгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒ
й»ҷеӯ—гҒҢйқһеёёгҒ«еӨҡгҒ„гҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҢгӮ·гӮ¬гғ„гӮ§гҖҚгҖҢгӮҝгӮ·гғ«гғігғқгҖҚгҒҜгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҖҒ
"gzhis ka rtse", "bkra shis lhun po" гҒЁи»ўеҶҷгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘз¶ҙгӮҠгҒ§иЎЁиЁҳгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ
и©ізҙ°гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҢгғҒгғҷгғғгғҲиӘһгҒ®гӮ«гӮҝгӮ«гғҠиЎЁиЁҳгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҚгҒӘгҒ©гҒ®й …зӣ®гӮ’еҸӮз…§гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%99%E3%83%83%E3%83%88%E8%AA%9E%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A%E8%A1%A8%E8%A8%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
>>29
гҒЎгӮғгӮ“гҒЁеӯҰж ЎгҒ«иЎҢгҒЈгҒҹгғҒгғҷгғғгғҲдәәгӮӮ
жңӘгҒ гҒ«жӯЈгҒ—гҒ„з¶ҙгӮҠгҒҢи§ЈгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгӮүгҒ—гҒ„гҖӮ
гҒӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰй»ҷеӯ—гӮ’е…ЁйғЁеүҠгҒЈгҒҹгӮүгҒқгӮҢгҒҜгҒқгӮҢгҒ§ж··д№ұгӮӮиө·гҒҚгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҒ—вҖҰ
ж–Үеӯ—гҒ®ж”№йқ©гҒҜйӣЈгҒ—гҒ„гҖӮ
ж·ұгҒ„гҒӘ
иӢұиӘһгӮӮгҖҒгӮ№гғҡгӮӨгғіиӘһгҒЁгҒӢгҒҝгҒҹгҒ„гҒ«зҷәйҹігҒ«иЎЁиЁҳгӮ’зөұдёҖгҒ—гӮҚгӮ„гғҮгғ–
гҒЁжҖқгҒҶгӮ“гҒ гҒ‘гҒ©иЎЁиЁҳгҒ®гҒ»гҒҶгҒҢи«–зҗҶзҡ„гҒ§ж„Ҹе‘ігҒҢйҖҡгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„гҒӢгӮү
з°ЎеҚҳгҒ«гҒ„гҒЈгҒ—гӮҮгҒ«гҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гӮ“гҒ гӮҲгҒӘ
гҒҫгҒҳгҒҠгӮҸгҒЈгҒЁгӮӢгӮҸ
д»–гҒ«гӮӮгғ•гғ©гғігӮ№иӘһгҒӘгҒ©гҖҒд»–гҒ®иЁҖиӘһгҒ«гӮӮй»ҷеӯ—гҒҜгҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жӯҙеҸІзҡ„д»®еҗҚйҒЈгҒ„гӮӮиҲҲе‘іж·ұгҒ„гҒ§гҒҷгӮҲгҖӮ
гҒёгғјгҒёгғјгҒёгғј
пҪ’гҒ®еүҚгҒ®пҪ—гҒҜзҷәйҹідёҠгҒ®ж„Ҹе‘ігҒҢиүҜгҒҸеҲҶгҒӢгӮӢгҖӮ
вҖңпјІвҖқгҒЈгҒҰдёӢе”ҮгӮ’еҸЈгҒ«е·»гҒҚиҫјгӮ“гҒ§гҖҢгҒҶгҒҶгғјгӮӢгҒЈгҖҚгҒЈгҒҰзҷәйҹігҒҷгӮӢгҒӢгӮүгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—пҪҺгҒ®еүҚгҒ®пҪӢгҒҜеҲҶгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒӘгҖӮ
иӘӯгҒҫгҒӘгҒ„ж–Үеӯ—гҒ«гӮӮдҫЎеҖӨгҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮӢ
дёҠгҒ«жҢҷгҒ’гҒҹгӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҖҒ
гҖҢзҷәйҹігҒ«й–ўдҝӮгҒ®гҒӘгҒ„ж–Үеӯ—гҒҜе…ЁгҒҰеүҠйҷӨгҒӣгӮҲгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгғ«гғјгғ«гҒ®з¶ҙгӮҠеӯ—ж”№йқ©жЎҲгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒknow гҒЁ noгҖҒknight гҒЁ nightгҖҒwrite гҒЁ riteгҖҒ
whole гҒЁ holeгҖҒpsychosis гҒЁ sycosis гҒҢ
гҒқгӮҢгҒһгӮҢеҗҢгҒҳз¶ҙгӮҠгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ“гҒЁгӮ’еҘҪгӮҖдәәгҒҜгҒӮгҒҫгӮҠеӨҡгҒҸгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒЈгҒҹгӮҝгӮӨгғ—гҒ®з¶ҙгӮҠеӯ—ж”№йқ©жЎҲгҒҜгӮ„гҒҜгӮҠеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҖӮ
https://www.geocities.jp/yomikata_spelling/silent-consonant-letters.html
жҳ”гҒ®дәәгҒҜгӮҜгғҠгӮӨгӮ°гғ•гғҲгҒЈгҒҰиӘӯгӮ“гҒ§гҒҹгҒЈгҒҰгҒ“гҒЁгҒ§гҒҠk?
>>39 gh гҒҜгӮӮгҒЁгӮӮгҒЁ/f/гҒ®зҷәйҹігҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
enough,laugh,toughгҒ«гҒқгҒ®еҗҚж®ӢгӮҠгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒеӨҡгҒҸгҒ®еҚҳиӘһгҒ§гҒҜзҷәйҹігҒ—гҒҘгӮүгҒ„гҒҹгӮҒгҒӘгҒ®гҒӢ次第гҒ«ж¶Ҳж»…гҒ—гҖҒ
з¶ҙгӮҠгҒ гҒ‘ж®ӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
>>40гҖҖиӘ¬жҳҺгҒҢи¶ігӮҠгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҖӮ
е®ҹйҡӣгҒҜghгҒҜиӘһдёӯгӮ„иӘһжң«гҒ§гғүгӮӨгғ„иӘһгҒ®"ich""Bach"гҒӘгҒ©гҒ®"ch"гҒ®зҷәйҹігҒ гҒЈгҒҹгҖӮ
зҸҫд»ЈгҒ§гҒҜй•·жҜҚйҹігҒ®еҫҢгҒ§гҒҜзҷәйҹігҒӣгҒҡгҖҒзҹӯжҜҚйҹігҒ®еҫҢгҒ§гҒҜ/f/гҒ®йҹігҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ
гҒӘгӮӢгҒ»гҒ©гҒҠгӮӮгҒ—гӮҚгҒ„
ж—Ҙжң¬иӘһгҒ§гҒҹгҒЁгҒҲгӮӢгҒӘгӮүгҖҢе’ҢжіүгҖҚгҒ®гҖҢе’ҢгҖҚгҒЁгҒӢгҖҢдјҠйҒ”гҖҚгҒ®гҖҢдјҠгҖҚгҒӘгҒ©гҒӢгҖӮ
еүҚиҖ…гҒҜең°еҗҚгӮ’жјўеӯ—пј’ж–Үеӯ—гҒ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҢе’ҢгҖҚгӮ’жҢҝе…ҘгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҖӮ
еҫҢиҖ…гҒҜжҳ”гҒҜгҖҢгҒ„гҒҹгҒҰгҖҚгҒЁзҷәйҹігҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҖҢгҒ„гҒ§гӮӢвҶ’гҒ§гӮӢгҖҚгҖҒгҖҢгҒ„гҒ гҒҸвҶ’гҒ гҒҸгҖҚгҒЁеҗҢгҒҳеӨүеҢ–гҒ§
гҖҢгҒ„гҖҚгҒҢжҠңгҒ‘иҗҪгҒЎгҖҒгҖҢгҒ гҒҰгҖҚгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒӘгҒ®гҒ§дәӢе®ҹдёҠгҖҢдјҠгҖҚгҒҢй»ҷеӯ—гҒ«гҖӮ
>>48 иЈңи¶іпјҡпјһеүҚиҖ…гҒҜең°еҗҚгӮ’жјўеӯ—пј’ж–Үеӯ—гҒ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҢе’ҢгҖҚгӮ’жҢҝе…ҘгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҜең°еӣігӮ„йўЁеңҹиЁҳгӮ’з·ЁзәӮгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒ«
ең°еҗҚгӮ’жјўеӯ—пј’ж–Үеӯ—гҒ«гҒ—гҒҹгҒ»гҒҶгҒҢйғҪеҗҲгҒҢиүҜгҒӢгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖӮ
|
|
гӮігғЎгғігғҲдёҖиҰ§ (47)
-
- 2022/05/18 15:33
- жҙ»зүҲеҚ°еҲ·гҒ®жҷ®еҸҠгҒ§зҷәйҹігҒҜжҺЁз§»гҒҷгӮӢгҒ®гҒ«з¶ҙгӮҠгҒҜеӣәе®ҡгҒ•гӮҢгҒЎгӮғгҒЈгҒҹгӮ“гҒ гҒЈгҒҰгҒӘ
-
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 15:50
- гӮҶгғјгҒҰnitгҒҳгӮғгғӢгғҲгҒҸгӮүгҒ„гҒ«гҒ—гҒӢиӘӯгӮҒгӮ“гҒ—гҖҒиӢұиӘһгҒЈгҒҰгҒ®гҒҜгҒҶгҒҫгҒҸгҒ§гҒҚгҒҰгӮӢгҒӯ
-
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 15:52
-
зҷәйҹіиЁҳеҸ·гӮӮй–ўдҝӮгҒ—гҒҰгӮӢгҒЈгҒҰгҒ®гӮӮгҒӮгӮӢгӮ“гҒ гӮҚгҒҶгҒ‘гҒ©гҒӘгҖӮ
гҒЎгҒӘгҒҝгҒ«гҖҒDecemberгӮ„NovemberгҒ®"b"гҒ®еүҚгҒҢдҪ•ж•…"n"гҒҳгӮғгҒӘгҒҸгҒҰ"m"гҒӘгҒ®гҒӢгҖӮ
гғҮгӮЈгғғгӮ»гғігғҗгғј/гғҺгғјгғҷгғігғҗгғј
гҖҢгғігҖҚгҒӘгӮү"n"гҒ§гҒ„гҒ„гҒҳгӮғгӮ“пјҒгҒЁж—Ҙжң¬дәәгҒҜгҒ„гҒҶгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜзҷәйҹіиЁҳеҸ·гҒ«иө·еӣ гҒҷгӮӢгҖӮ
иӢұиӘһгҒ®зҷәйҹігҒҜиҲҢгӮ„е”ҮгҒ®еӢ•гҒҚгҒҢйҮҚиҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгҒҢгҖҒmгҒ®зҷәйҹігҒҳгӮғгҒӘгҒ„гҒЁе”ҮгӮ’й–үгҒҳгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ
пјҲ"m"гҒ®зҷәйҹігҒҜ"гӮЁгғігғ "гҒ§жңҖеҫҢгҒ®гғ гҒҜгҖҒеҘігҒҢеҸЈзҙ…гҒӨгҒ‘гҒҰгҖҢгғігғғгғ‘пјҒгҖҚгҒЈгҒҰгҒҷгӮӢжҷӮгҒҝгҒҹгҒ„гҒ«е”ҮгӮ’й–үгҒҳгӮӢгҖӮ"n"гҒҜгҖҢгӮЁгғігғҢгҖҚгҒ гҒӢгӮүеҹәжң¬еҸЈгҒҜз©әгҒ‘гҒҹгҒҫгҒҫпјү
гҒқгҒ—гҒҰе”ҮгӮ’й–үгҒҳгҒӘгҒ„гҒЁж¬ЎгҒ®"b"=гғҗиЎҢпјқжҝҒйҹігӮ’еҮәгҒӣгҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҖҒиҮӘ然гҒ«bгҒ®еүҚгҒҜmгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ
гғ»гғ»гғ»гҒ§гӮӮгҒҫгҒӮгҖҒгҒ©гҒҶгҒӣж—Ҙжң¬дәәгҒҜзҷәйҹідёӢжүӢгҒ гҒӢгӮүгҒқгӮӮгҒқгӮӮж°—гҒ«гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгӮӮгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҒҢгҖӮmbгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒҢkгӮ„ghгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒҢпҪ— -
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 15:53
- гҒ“гҒҶгҒ„гҒҶдҪҝгҒҲгӮӢзҹҘиӯҳгӮ№гғ¬жҜҺз§’жҠ•зЁҝгҒ—гҒҰгҒ»гҒ—гҒ„
-
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 15:56
- гғҜгӮӨгҒ®гӮҜгғ©гӮ№гҒ§гҒ®еӯҳеңЁж„ҹгҒҝгҒҹгҒ„гӮ„гҒӘ
-
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 16:04
- 80гҒёгҒҮ
-
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 16:07
- гғӣгғігӮ°гӮігғігӮ°
-
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 16:09
-
жҳ”гҒҜзҷәйҹігҒ—гҒҰгҒҹгӮ“гҒ гҒӘ
гҒҳгӮғгҒӮknightгҒҜгӮҜгғҠгӮӨгӮ°гғҲгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒӢ -
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 16:11
- дјҠйҒ”гҒЁе’ҢжіүгҒҢеӢүеј·гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгӮҸ
-
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 16:16
-
еӨ–еӣҪдәәгҒҢиҰӢгӮӢ
йҮҚгӮ„з”ҹгҒҜгҒ»гӮ“гҒЁдёҚиҰӘеҲҮгҒ гҒЁжҖқгҒҶ -
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 16:21
- гғүгӮӨгғ„иӘһгҖҒгғ•гғ©гғігӮ№иӘһгӮ’гҒӢгҒҳгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ“гҒ®иҫәгӮҠгҒ®зҗҶи§ЈгҒҢгҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮӢ
-
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 16:23
-
гғҒгғҷгғғгғҲгҒҜеұұеӣҪгҒ гҒӢгӮүзҷәйҹігҒҢгҒӢгҒӘгӮҠйҒ•гҒҶеӨҡзЁ®еӨҡж§ҳгҒӘж–№иЁҖгҒҢеҗ„ең°гҒ«гҒӮгӮӢгҒ—гҖҒгғҒгғҷгғғгғҲиӘһеңҸгҒҜгғ–гғјгӮҝгғігӮ„гӮӨгғігғүгҒ®гғ©гғҖгғғгӮҜгҖҒгӮ·гғғгӮӯгғ гҒӘгҒ©еӣҪеӨ–гҒ«гӮӮеәғгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢ
й»ҷеӯ—гӮ’еүҠйҷӨгҒ—гҒӘгҒ„гҒ®гҒҜе…ұйҖҡгҒ®ж–ҮиӘһгӮ’жҢҒгҒӨгҒ“гҒЁгҒ§ж–ҮеҢ–зҡ„гҒӘз№ӢгҒҢгӮҠгӮ’з¶ӯжҢҒгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігӮӮгҒӮгӮӢ -
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 16:34
-
KгҒ®йҹігҒҢж¶ҲгҒҲгҒЎгӮғгҒҶгҒ®гҒЈгҒҰгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜж—Ҙжң¬иӘһгҒ«гӮӮгҒӮгӮӢзҸҫиұЎгҒ гӮҲгҒӯпјҹ
иӢұиӘһгҒ®гҒЁгӮӮдҪ•гҒӢй–ўйҖЈгҒӮгӮҠгҒқгҒҶгҖӮ
гҖҢжӣёгҒҸгҖҚвҶ’гҖҢжӣёгҒҚгҒҰгҖҚвҶ’гҖҢжӣёгҒ„гҒҰгҖҚ
гҖҢгӮҲгҒҸгҖҚвҶ’гҖҢгӮҲгҒҶгҖҚ
гҖҢгӮҲгӮҚгҒ—гҒҸгҖҚвҶ’гҖҢгӮҲгӮҚгҒ—гӮ…гҒҶгҖҚ
гҖҢжӮІгҒ—гҒҚгҖҚвҶ’гҖҢжӮІгҒ—гҒ„гҖҚ -
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 16:57
-
гғ•гғ©гғігӮ№иӘһгҒҜhгҒ«зӣёеҪ“гҒҷгӮӢеӯҗйҹігҒҢгҒӘгҒ„гӮүгҒ—гҒ„
иӢұиӘһеңҸгҒ®hourгҒ§hгҒҢгҒӘгҒ„гҒ®гӮӮгҒқгӮҢгҒ«й–ўйҖЈгҒҷгӮӢгӮ“гҒҳгӮғгҒӘгҒ„гҒӢгҒӘ -
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 17:01
-
пјһиӢұиӘһгҒ«гҒҜгҖҢгғӢгғЈгғ»гғӢгғҘгғ»гғӢгғ§гҖҚгҒ®зҷәйҹігҒҢдҪҝгӮҸгӮҢгҒӘгҒ„
гғӢгғЈгғјгӮ№гҒ®иӢұиӘһеҗҚгҒҜ MeowthгҒӘгҒ®гҒӢгҖӮд№ій ӯгҒЁгҒӢе°ҝйҒ“гҒЁгҒӢдјқгҒҲгҒҹгҒ„е ҙеҗҲгҒҜгҒ©гҒҶгҒҷгӮӢгӮ“гҒҳгӮғ -
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 17:09
- гғ•гғ©гғігӮ№гҒ§гҒҜHгҒ®жҷӮеЈ°гӮ’еҮәгҒ•гҒӘгҒ„гӮүгҒ—гҒ„гҒ®гӮігғ”гғҡгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒ®гҒ«гӮігғЎж¬„гҒ«гӮӮгҒӘгҒ„гҒӘгӮ“гҒҰ
-
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 17:11
- whiteгҒҢгғҜгӮӨгғҲгҒ«гҒ—гҒӢиҒһгҒ“гҒҲгҒӘгҒ„гҒ®гҒҜиӢұиӘһгӮ’зҷәйҹігҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒ«ж··д№ұгҒ—гҒҹ
-
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 17:13
-
е’ҢжіүгҒҜгҖҖгҒ„гҒҡгҒҝгҒ®гҒ„гҒҢгӮҗгҒ гҒӢгӮүгҒӘгҒ®гҒӢгҒЁ
еӢқжүӢгҒ«жҖқгҒЈгҒҰгҒҹ
-
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 17:14
- HongKongгҒ®гҒ“гҒЁгҒӢгғјпјҒ
-
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 17:43
-
гҒқгӮҚгҒқгӮҚгғҗгғјгӮёгғ§гғігӮўгғғгғ—гҒ—гӮҚ
i luv u гҒЁгҒӢгӮҒгҒЈгҒЎгӮғеҠ№зҺҮзҡ„гҒ§гҒҷгҒҚ -
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 18:18
- иӢұиӘһгҒ®е°ҸгғҚгӮҝгҒ§жңүеҗҚгҒӘghotiпјҲfishгҒЁеҗҢйҹіпјүгҒҜе…ЁйҹізҜҖгҒҢй»ҷеӯ—гҒЁгӮӮгҒҝгҒӘгҒӣгӮӢгҒЈгҒҰи©ұгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒӘ
-
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 18:51
-
knife
KгӮ’иӘӯгҒҫгҒӘгҒ„гҒЁгғҠгӮӨгғ•
feгӮ’иӘӯгҒҫгҒӘгҒ„гҒЁгҒҸгҒӘгҒ„
гҒ©гҒЈгҒЎгӮӮеҲғзү© -
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 18:59
- еүҚз”°ж—ҘжҳҺгҒ®гҖҺж—ҘгҖҸгӮӮгҒқгҒҶгҒ гӮҲгҒӘгҖӮ
-
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 19:04
- гҒ“гӮҢгҒҜиүҜгӮ№гғ¬
-
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 19:05
-
иӢұиӘһгҒҜеҸӨд»Јгғ–гғӘгғҶгғіеі¶гҒ®йғЁж—ҸгҒӢгӮү欧е·һеӨ§йҷёгҒ®и«ёж—ҸгҒҫгҒ§еҚҳиӘһгҒЁгӮ№гғҡгғ«гҒҢгҒ”гҒЎгӮғгҒҫгҒңгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгӮӢгҒӢгӮүгҒӘ
еҚҳиӘһгҒ®гӮ№гғҡгғ«гӮігғігғҶгӮ№гғҲгҒҝгҒҹгҒ„гҒӘгҒ®гӮ„гҒЈгҒҰгӮ“гҒӯгӮ“гҒ§ -
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 19:10
-
еӯҰгҒ¶гҒ®гҒЈгҒҰгғҶгӮ№гғҲгҒ§иүҜгҒ„зӮ№еҸ–гӮӢзӮәгҒ«гҒҷгӮӢгғўгғігҒҳгӮғгҒӘгҒҸ
зҹҘзҡ„еҘҪеҘҮеҝғгӮ’жәҖгҒҹгҒҷзӮәгҒ®гғўгғігҒӘгӮ“гӮҲгҒӘжң¬жқҘгҒҜ -
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 20:40
-
д»ҠгҒ§гҒ“гҒқдё–з•ҢиЁҖиӘһгғ…гғ©гҒ—гҒҰгӮӢгҒҢ
жң¬жқҘгғЁгғјгғӯгғғгғ‘дё–з•ҢгҒ®з”°иҲҺиЁҖиӘһгҒ гӮӮгӮ“гҒӘ
гӮ№гӮ«гғігӮёгғҠгғ“гӮўгҒ«гӮІгғ«гғһгғігҖҒгғ•гғ©гғігӮ№гҒ®еҜ„гҒӣйӣҶгӮҒгҒ®гҒҸгҒӣгҒ«
зҷәйҹігҒҢгҒ©гҒҶгҒ®гҒ“гҒҶгҒ®иЁҖгҒЈгҒҰгӮӢ
гҒҠеүҚгӮүгҒ®иЁҖиӘһгҒҢгҒҫгҒҡиЁӣгҒЈгҒҰгӮӢгӮ“гҒ гӮҲгҖҒгҒЁиЁҖгҒ„гҒҹгҒ„ -
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 21:30
- еҚҳиӘһд»ҘеӨ–гҒ«гӮӮгӮ№гғ”гғјгӮӯгғігӮ°гҒ§гҒ®йҹіеЈ°еӨүеҢ–гҒ§hisгҖҒherгҒ®hгӮ’зҷәйҹігҒ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒеҸЈиӘһгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰwannaгҖҒgannaгҒ®иЎЁиЁҳгҒҢз”ҹгҒҫгӮҢгҒҹгӮҠгҒ§дјјгҒҹгӮҲгҒҶгҒӘеӨүеҢ–гҒҢгҒӮгӮӢгӮҲгҒӯ
-
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 21:33
- дёӯеӣҪиӘһгҒ®гғ”гғігӮӨгғігҒ§жіЈгҒ„гҒҰгӮӢгҖӮ
-
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/18 22:54
-
иӘӯгҒҫгҒӘгҒ„зҗҶз”ұгӮ’иӘ¬жҳҺгҒҷгӮӢгӮҲвҶ’гҖҢй»ҷеӯ—гҖҚгҒЁгҒ„гҒ„жҷӮд»ЈгҒ®жөҒгӮҢгҒ§зҷәйҹігҒ•гӮҢгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹ
зҗҶз”ұгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒӘгҒҸгҒӯпјҹ -
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/05/24 14:32
-
гҒҝгӮ“гҒӘгҖҒгҖҢгҒ“гҒ®гӮігғЎгғігғҲгҒ«иҝ”дҝЎгҖҚгғңгӮҝгғігӮ’дҪҝгҒҠгҒҶгҒң
-
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
-
- 2022/06/17 23:02
- зҙҖдјҠгӮӮзҙҖгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гӮ’дәҢж–Үеӯ—гҒ«гҒ—гҒҹдҫӢгҒ гҒӯ
-
0

bipblog
гҒҢ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ



 гҖҗеҜқиҗҪгҒЎASMR17жҷӮй–“гҖ‘д»ҠгҒҷгҒҗзң гӮҠгҒҹгҒ„еҗӣгӮ’гҒЁгҒ“гҒЁгӮ“еҜқгҒӢгҒ—гҒӨгҒ‘гӮӢзҷ’гҒ—еЁҳгҖӮи„ігҒҢгҒЁгӮҚгҒ‘гӮӢгҒЁгҒ“гҒЁгӮ“е®үзң и©°гӮҒеҗҲгӮҸгҒӣ[е‘ЁйҳІгғ‘гғҲгғ©]
гҖҗеҜқиҗҪгҒЎASMR17жҷӮй–“гҖ‘д»ҠгҒҷгҒҗзң гӮҠгҒҹгҒ„еҗӣгӮ’гҒЁгҒ“гҒЁгӮ“еҜқгҒӢгҒ—гҒӨгҒ‘гӮӢзҷ’гҒ—еЁҳгҖӮи„ігҒҢгҒЁгӮҚгҒ‘гӮӢгҒЁгҒ“гҒЁгӮ“е®үзң и©°гӮҒеҗҲгӮҸгҒӣ[е‘ЁйҳІгғ‘гғҲгғ©] гҖҗгғ–гғ«гғјгӮўгғјгӮ«гӮӨгғ–гҖ‘гғҰгӮҰгӮ«ASMRпҪһй ‘ејөгӮӢгҒӮгҒӘгҒҹгҒ®гҒҷгҒҗгҒқгҒ°гҒ«пҪһ
гҖҗгғ–гғ«гғјгӮўгғјгӮ«гӮӨгғ–гҖ‘гғҰгӮҰгӮ«ASMRпҪһй ‘ејөгӮӢгҒӮгҒӘгҒҹгҒ®гҒҷгҒҗгҒқгҒ°гҒ«пҪһ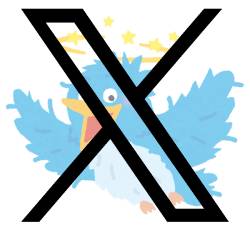

жҜҺж—ҘгӮ„гӮҢ
bipblog
гҒҢ гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ